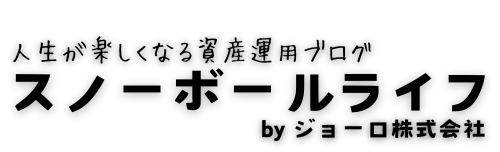長期投資では相場の上げ下げに一喜一憂する必要はありません。それでも、資産運用を始めるにあたり、経済情勢や金融市場の状況を教えてほしいとの意見が多いので、ざっくり無理くり、ここ数年の概況をお伝えします。
概況
各国で強弱があるものの、全体でみると世界の株式は上昇基調を継続しています。

100年に1度の金融危機と言われるリーマンショックが2008年に発生しました。
対応として各国が政策金利の引き下げ(利下げ→金利が低下→個人や企業の借り入れが増える→買い物や投資に使えるお金が増える→モノやサービスの売れ行きが伸びる→モノやサービスの価格が上昇→経済成長が加速)をしたり、金融市場にマネーを大量供給する量的緩和策を実施したことで、2013年には米欧の代表的な株価指数が史上最高値を更新しました。
その後も細かなことはいろいろとありましたが、上昇基調を継続していた世界株式。2020年に新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、一時下落したものの、ワクチン開発の進展や企業活動の再開などから、年内には上昇に転じました。
しかし、生産や流通体制がコロナ禍から復活できておらず、供給が追い付かなくてモノやサービスの価格が上昇する世界的なインフレに突入。
また、2022年に、ウクライナに侵攻したロシアに対して各国が経済制裁を科し、ロシアからの資源輸入を減らしたことで、原油などの資源価格が急騰し、インフレに拍車がかかりました。
このような中、米欧の中央銀行が政策金利の引き上げを実施(利上げ→金利が上昇→個人や企業の借り入れが減る→買い物や投資に使えるお金が減る→モノやサービスの売れ行きが鈍る→モノやサービスの価格が下落→経済成長が減速)したことを背景に、世界株式は上昇幅を縮小。
2023年になると、インフレが落ち着きつつあり、利上げによる景気減速が懸念されるようになったので、米欧が利下げ方針に転換。企業の業績改善もあって2024年には米欧の株式市場が何度も史上最高値を更新しました。
日本は世界で最後のマイナス金利政策をようやく3月に終了。金利差の縮小から本来であれば米ドルやユーロに対して円高に進んでもおかしくないですが、金利の低い円は売られる傾向が続き、1米ドル=160円台後半と、37年半ぶりの水準まで円安・米ドル高円安が進行。日経平均株価は1989年のバブル期につけた史上最高値を更新しました。
今後について
足元の不安材料としては、長期化するロシアとウクライナを巡る紛争、イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突が続く中東情勢、アメリカと中国の貿易摩擦、先進国における財政上の課題、アメリカの大統領選挙、フランスの国民議会選挙などが挙げられます。
列挙してみると、結構沢山ありますよね…でも、残念ながら〇〇ショックと呼ばれるような暴落のタイミングは誰にも予測できません。過去の暴落はその中身が毎回異なり、「何それ?」と初めて聞くような危機が突然やってきます。
長期間の資産運用では、もし暴落しても狼狽売りするのではなく、投資を継続することが大事です。基本的な動向を知っておくことは重要かもしれませんが、未来は予測できないと割り切って「長期・積立・分散」でゆっくり継続していきましょう。
資本主義経済が続く限り「豊かになりたい」「夢をかなえたい」という人々の欲望を原動力に、世界中の企業が努力して前進していきます。そういった企業活動の総体である世界経済は短期的な上げ下げをくり返しながら、これまでと同様に長期的には右肩上がりに成長すると考えています。
本日はここまで。それでは、チャオチャオ!